相談相手はAIに!?知識共有の新しい形! Google「 NotebookLM」ウェブアクセシビリティの専門家を作ってみた。
ブログ
2025.03.31
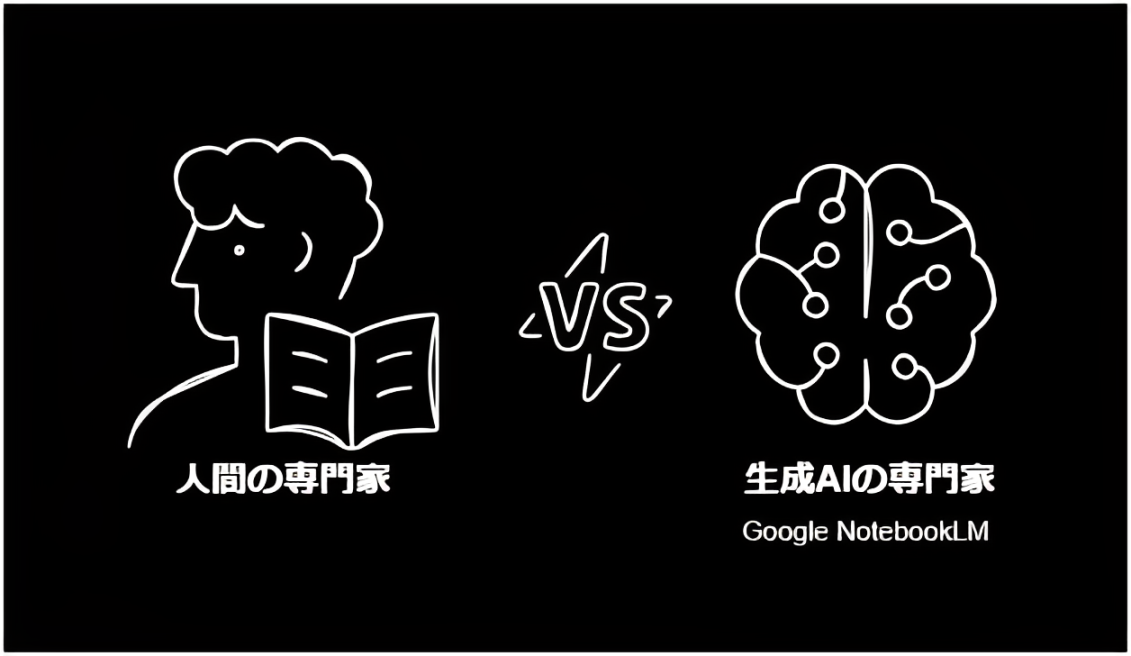
社内で特定の領域に詳しい人がいると、仕事で困ったときに相談できて心強いですよね。
しかし、相談される側の負担を考えたことはあるでしょうか?
社内で特定の領域に詳しい人がいると、仕事で困ったときに相談できて心強いですよね。
しかし、相談される側の負担を考えたことはあるでしょうか?
「いつも同じことを聞かれる」
「違う人から同じ内容の質問がくる」
こうした状況は多くの企業で見られるかもしれません。
調べれば分かることでも、
相談しやすい相手がいると「聞いたほうが早い」と頼ってしまいがちです。
また、自身で調べた事であっても自信が持てず・・・
生成AIが相談相手になる時代
例えば、Google 「NotebookLM」のようなツールを活用し、
社内のナレッジやブログをAIの学習データとして利用することで、
AIが適切な回答を提供することが可能になります。
これにより
- よくある質問の自動回答:何度も聞かれる基本的な質問にはAIが対応。
- ナレッジの蓄積と活用:ブログや社内の情報をAIに学習させ、必要な情報を即座に取得。
- 相談内容の整理:相談前にAIを活用することで、より具体的な質問ができるようになる。
この仕組みを導入することで、
✅ 相談される側の負担が軽減
✅ 相談する側も高品質な回答を迅速に得られる
✅ 社内の知識が蓄積され、組織全体の生産性が向上
といったメリットが生まれます。
試しに、ウェブアクセシビリティの専門家を
Google 「NotebookLM」で作ってみる
デジタル庁のウェブアクセシビリティ導入ガイドブック
https://www.digital.go.jp/resources/introduction-to-web-accessibility-guidebook
社内でウェブアクセシビリティに準拠したサイト設計の指針としている
デジタル庁が公開しているガイドブックです。
社内にもウェブアクセシビリティ専門家は存在していますが、
人間の専門家に「聞いたほうが早い」ではタイパが悪いです。
また、ウェブアクセシビリティ知識のない状態で
ウェブアクセシビリティについて調べる作業も骨がおれる作業となり非効率です。
今回、デジタル庁のウェブアクセシビリティ導入ガイドブックを
ソース(情報元)として活用「NotebookLM」で相談先となるウェブアクセシビリティ専門家を作っていきます。
メインのソースはこちら

